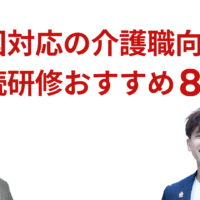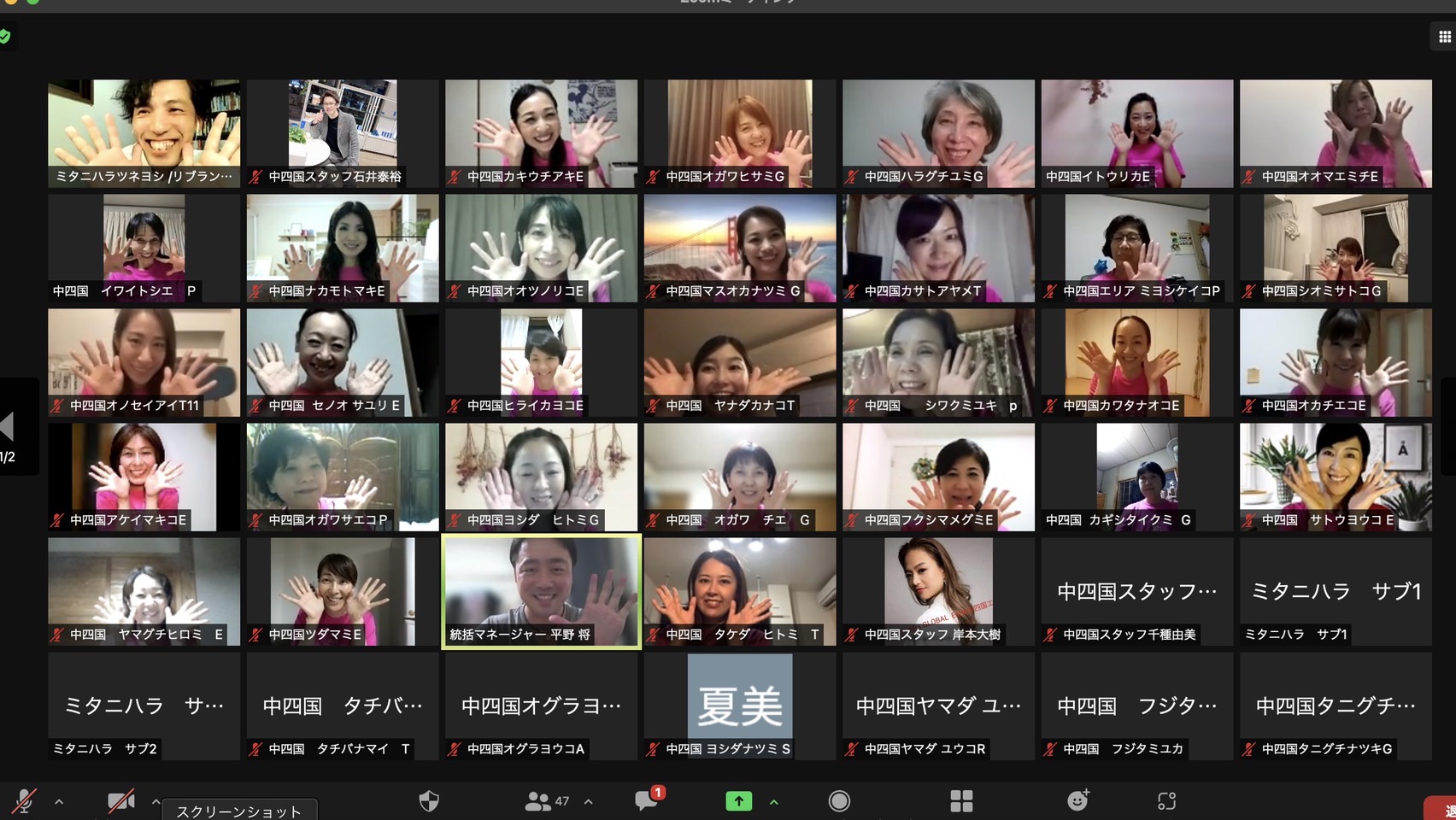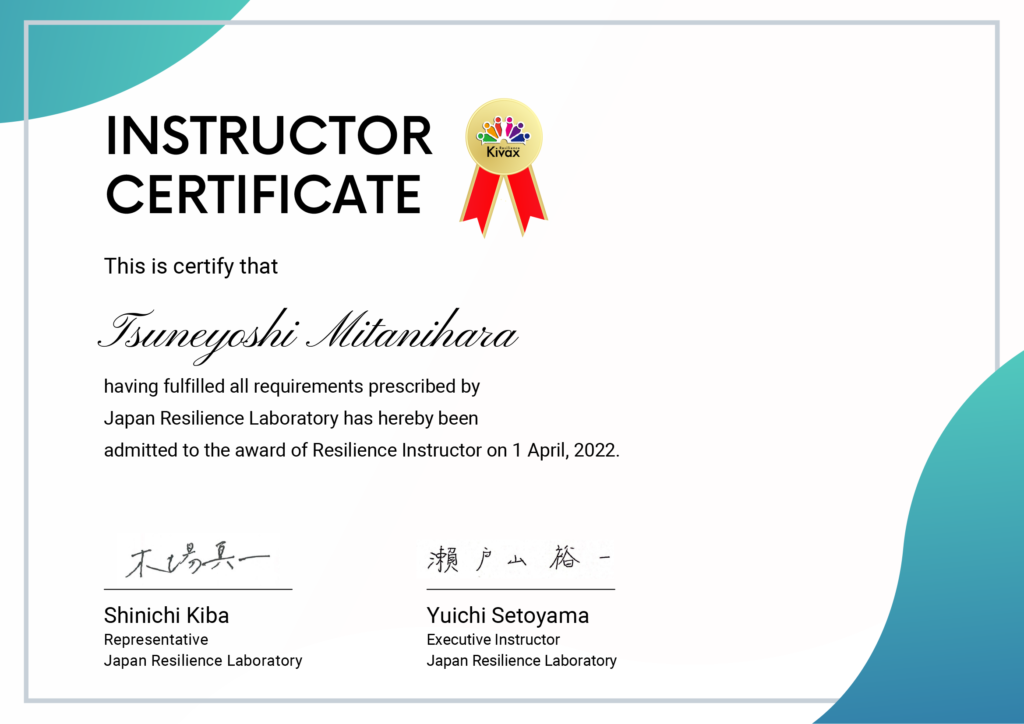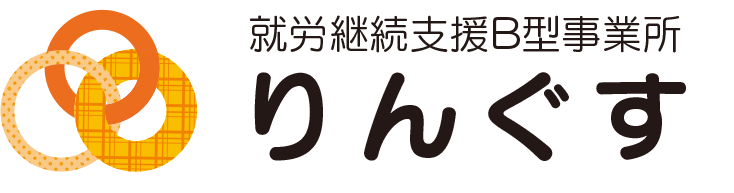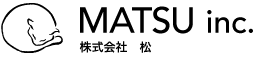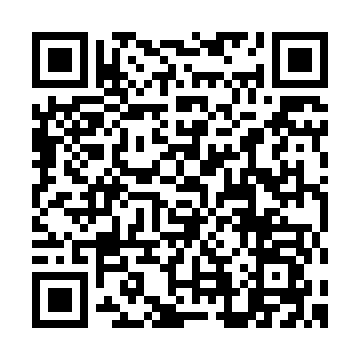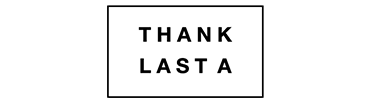こんにちは、サンク・ラスタ株式会社代表の三谷原恒良です。
私はレジリエンス(逆境から立ち直る力)を専門とし、日々企業研修や講演で組織の人材育成支援に携わっています。
今日は「“働きやすさ”だけではもう限界?社員が燃え尽きる会社に共通する意外な原因」というテーマでお話ししましょう。
最近、私の知人が経営する会社でこんな相談を受けました。
「うちは残業も少なく有給も取りやすい、働きやすさを徹底しているのに、なぜか社員の離職が止まらないんだ。いったい何が問題なんだろう?」
一見すると理想的な「ホワイト企業」です。
残業ゼロ、給与も平均以上、福利厚生も充実、上司も優しい。
それでも社員が次々と辞めていく…。
実はこれ、決して珍しいケースではありません。
働きやすい環境を整えたのに社員が燃え尽きたり辞めたりする背景には、ある“意外な共通原因”が潜んでいるのです。
目次
「働きやすさ」と「働きがい」は別物!~条件だけでは人は定着しない~
まず押さえておきたいのは、「働きやすさ」と「働きがい」は似て非なるものだという点です。
心理学者ハーズバーグの動機づけ・衛生理論によれば、労働時間や休日、給与、職場の人間関係などの「働きやすさ」に関する要素(衛生要因)は、不足すると不満になりますが、十分でもそれ自体で人に満足ややる気を与えるわけではありません。
一方で「働きがい」(動機づけ要因)となるのは、仕事の達成感や成長機会、責任、承認などであり、こちらが満たされてこそ人は心から満足し動機づけられるのです。
知人の会社でも「とにかく社員に楽をさせよう」という善意から残業ゼロや高待遇を実現しました。
しかし社員からは「このままで自分は成長できるのか?」「この会社で働く意義が感じられない」といった声が上がっていたのです。
これはまさに“働きやすさの限界”を示しています。
どんなに給与を上げても、快適なオフィス環境にしても、それだけで社員の情熱を永遠に燃やし続けることはできません。実際、厚生労働省の調査でも離職理由のトップ3は「労働条件の悪さ」「職場の人間関係」「給与の低さ」の順であり、給与が原因で辞める人は思ったほど多くないことが分かっています(男性7.6%・女性6.8%にとどまる)。
極端に言えば、給与の額だけで離職率が決まるならば高給の会社ほど離職率は低いはずですが、現実には高給でも離職率が高い会社が数多く存在します。
つまり、働く環境の良さ“だけ”では社員の心を繋ぎとめるには不十分なのです。
では、「働きがい」を高めるにはどうすれば良いのでしょうか?キーワードは「成長」と「目的」です。
人は自分が成長していると実感できるとき、あるいは自分の仕事が社会や誰かの役に立っていると感じられるときに、強い意欲を持てるものです。
最近では、働き方改革で生まれた「ぬるいホワイト企業」(残業少なく休みやすい高待遇な会社)ほど、優秀な若手ほど敬遠するという皮肉な現象も指摘されています。
一見申し分ない職場なのに、「このままでは市場価値の低い“ゆでガエル”になってしまうのでは」と不安を感じ、むしろ将来への危機感から退職を選ぶ若手もいるのです。
上司は聞いているつもり…でも部下はそう感じてない?~コミュニケーションの落とし穴~
「働きやすさ」の追求だけでは不十分な理由の一つに、上司と部下のコミュニケーション不全があります。
冒頭の知人の会社でも、「うちの管理職は部下の声に耳を傾けているはずなのに、なぜか部下は『聞いてくれない』と感じている」というズレが起きていました。
詳しく話を聞いてみると、そこには“質問”と“詰問”の取り違えという問題があったのです。
ある若手社員がミスを報告した際のこと。上司は次々と尋ねました。
「なんでこんなミスしたの?」「事前に確認はしなかったのか?」「原因は何なんだ?」
──上司自身は「部下に質問して問題解決を図ろう」と思っていたそうです。
しかし当の部下はどう感じたでしょうか?矢継ぎ早の問いに萎縮し、「責められている」「結局何を言っても怒られるだけだ」と感じて心を閉ざしてしまったのです。
これでは部下は育ちませんし、上司は「自分は聞いているつもり」でも部下からすれば「全然話を聞いてもらえない」という不満だけが残ってしまいます。
ポイントは「傾聴」と「承認」です。部下が何か失敗を報告してきたら、まず相手の話を最後まで聞く。
「そうか、そんなことがあったんだね」と相手の気持ちを受け止める一言を返すだけでも、部下の安心感は違います。
また、部下の努力や成長を小まめに認めて褒めることも大切です。人は誰しも認められたい、褒められたい欲求があります。
「上司の魅力」「会社の魅力」がないと若手は辞める
特に新卒をはじめとする若手社員の場合、直属の上司への尊敬や信頼があるかどうかが、「この会社で頑張り続けたいか」の判断基準になります。
極端に言えば「新入社員が3年以内に辞める理由は2つしかない。1つは会社に魅力がないこと、もう1つは上司に魅力がないこと」とも言われます。
厚生労働省の統計によると、新卒で入社した大卒社員の3年以内離職率は約30~35%にのぼります。これは「当たり前」とすら言われる時代です。
企業としては、採用した若手に長く活躍してもらうために、従来以上に早期から手厚いフォローが必要になっています。
仕事のミスマッチ(期待と現実のギャップ)、成長機会の欠如、上司との人間関係の悪さ――これらが三大要因です。
【燃え尽きを防ぎ、社員のレジリエンスを高めるために】
社員が燃え尽きずイキイキと働ける職場を作るにはどうすればいいのか?
ここで「レジリエンス(Resilience)」の視点が大事になります。
個人のレジリエンスを高めるには、日頃からストレスに対処するスキルや気持ちの切り替え方を学ぶことが有効です。
それ以上に、組織としてのレジリエンス、つまり「折れない組織風土」を作ることが必要です。
具体的には、心理的安全性、チームでのフォロー体制、ビジョンの共有、仕事の意義づけなどです。
【まとめ】
「働きやすさ」だけでは限界があります。社員が本当に求めているのは、「成長できる環境」「信頼できる上司」「社会的意義を感じられる仕事」です。
レジリエンスの高い組織づくりを進めることが、これからの企業経営のカギを握ります。
私たちサンク・ラスタ株式会社では、レジリエンスを軸にした研修・講演を通じて、組織の定着率向上・活力創出をサポートしています。
ご相談やご依頼は、お気軽にお問い合わせください。